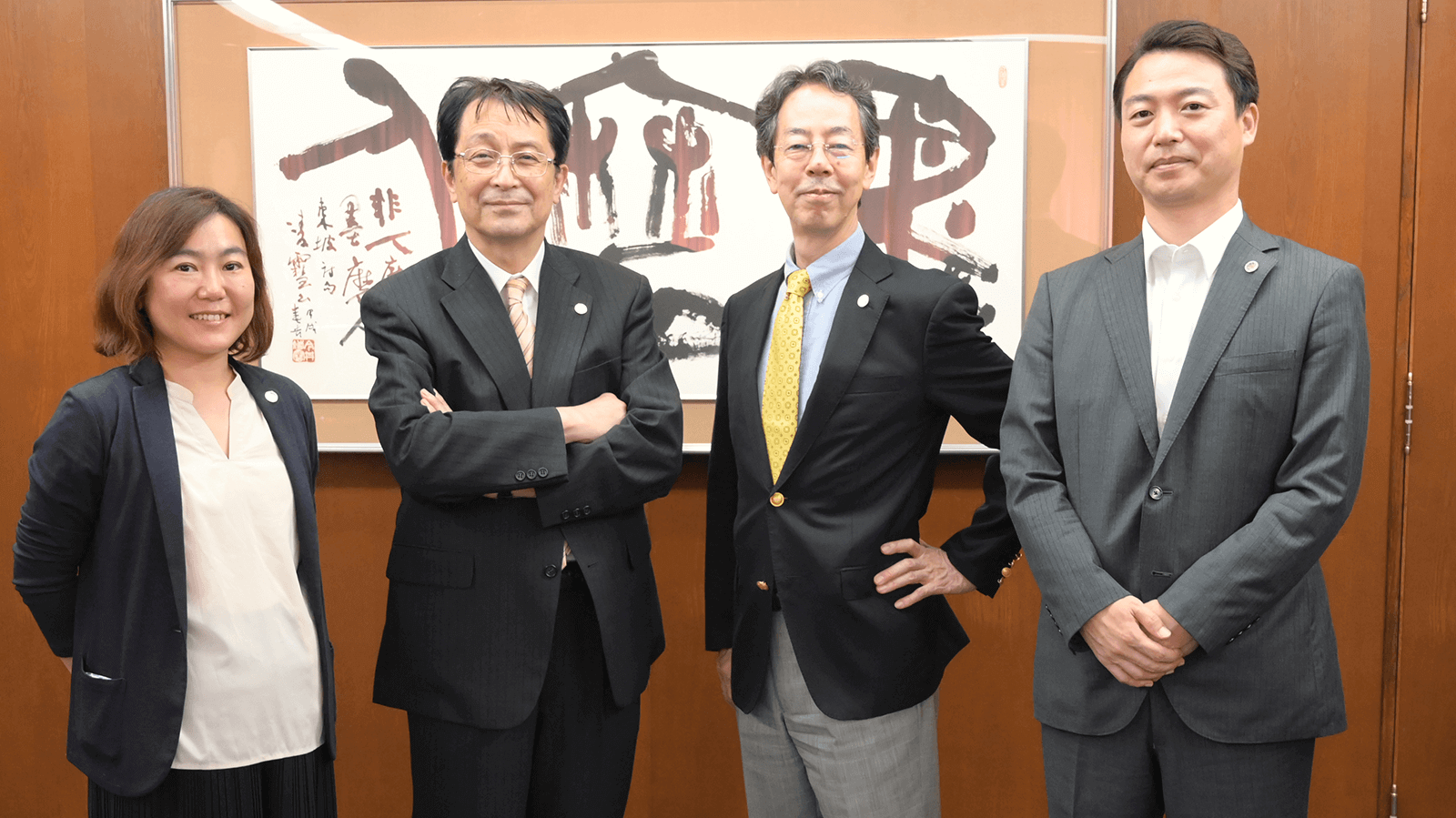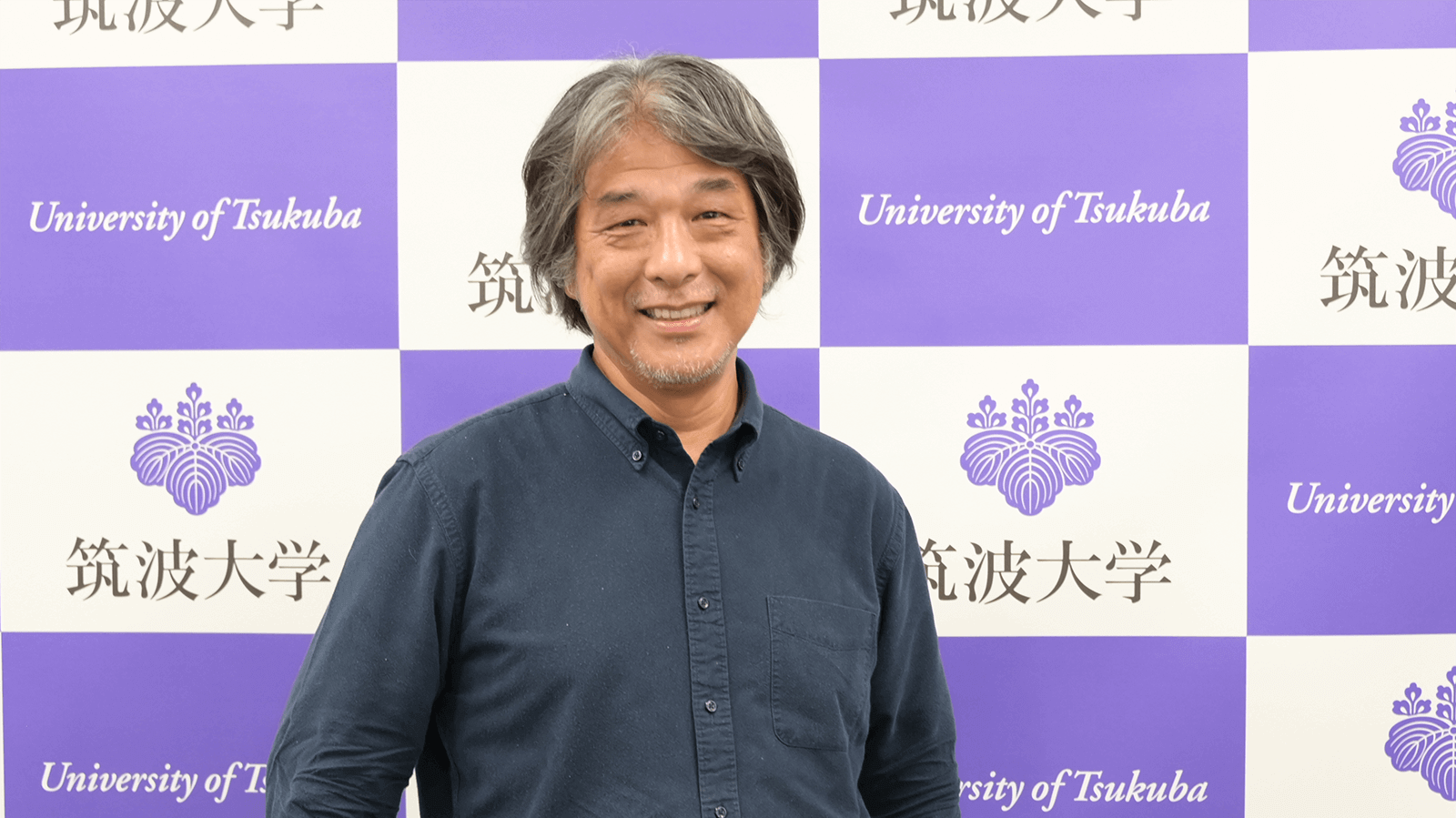研究を学者の手に取り戻すために―筑波大学の改革マインドが問いなおす、学術出版と大学ランキングの未来
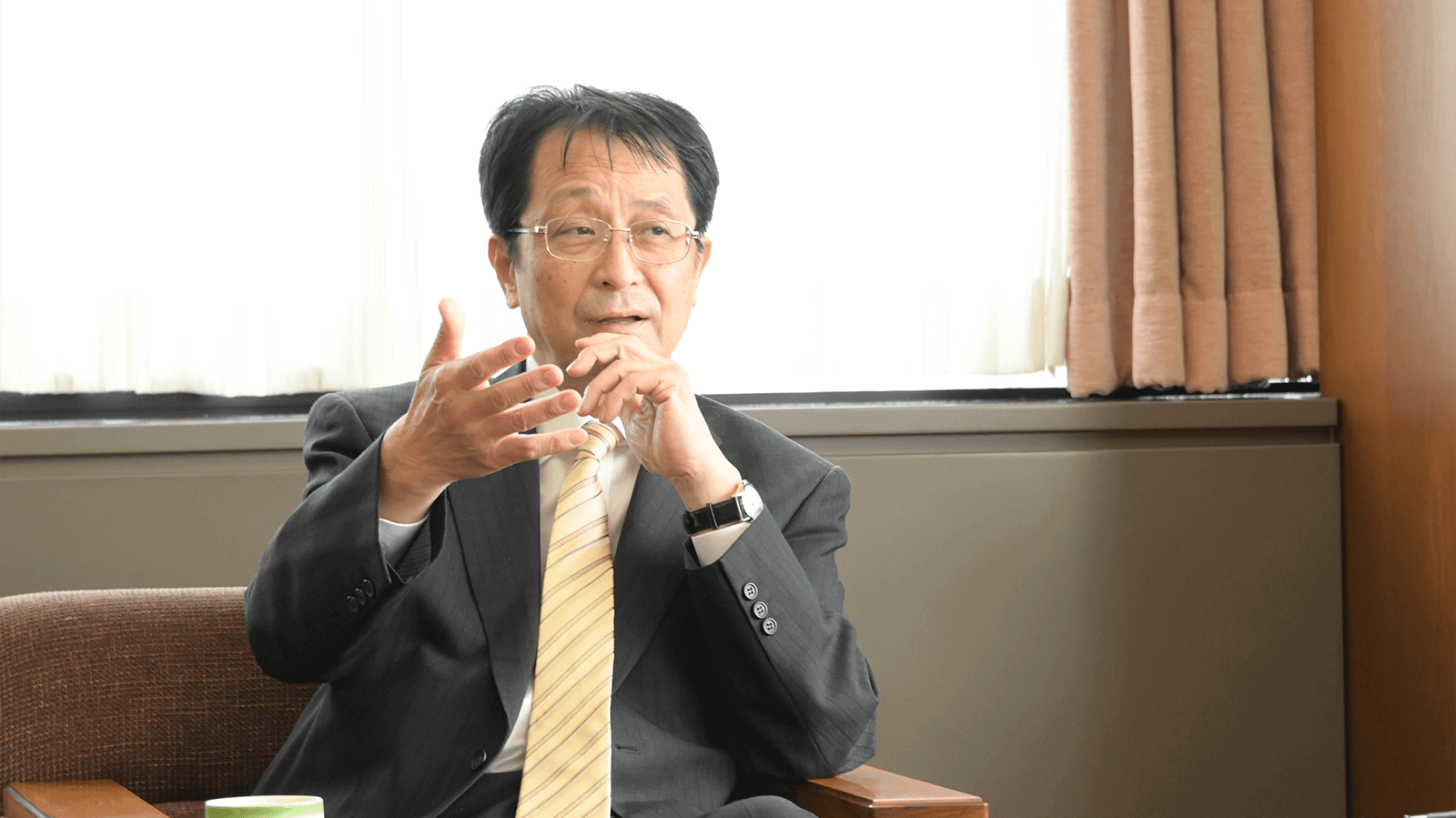
改革を理念に持つ大学に現れた、生粋の改革者。筑波大学が独自のオープンリサーチ出版ゲートウェイを国立大学とは思えない類稀なるスピードで実装できたのは、学長の「面白いじゃないか。失敗をおそれずとにかくやってみよう」という強い後押しがあったからだ、と現場の職員は口を揃えて言う。近年高まる学術出版の問題に日本から最初の一石を投じたのは、なぜ筑波大学だったのか?永田恭介学長本人に、そのこころを尋ねた。
—筑波大学が独自のオープンリサーチ出版ゲートウェイ導入に踏み切った決断には、大手学術出版社への強いメッセージ性を感じます。
「科学者の手に、学者の手に、研究の主体を戻さなければいけない」、我々が投げかけたい最も重要なメッセージはこれに尽きます。研究をしてそれを発表する責任は本来研究者にあり、研究の主導権は研究する側になければいけないはずです。しかし今の学術出版は、不動産業者のような出版の「仲介者」である出版社があまりにも主体となりすぎている。これではいけないと思うわけです。
研究者は研究の「生産者」であり、研究成果は多くの人に読まれ、公共財として幅広く消費され世界中で利用されるべきです。しかし、大手商業出版社が作り上げた今の仕組みでは、出版社側が掲載の決定権と著作権を持っていて、研究者自身にはそのどちらもコントロールすることができない。これが第一の、根本的な現代の学術出版の問題です。
そして第二に、今の大手出版社が研究者から二重利益を得ているという問題があります。研究者が論文を書いて投稿して採択されると、まずは高額な雑誌への掲載料を取られる。1本論文を書くと掲載料に40万や50万かかる場合もあり、僕の専門の生命科学分野などでは、年間10本書を書くこともありますが、そうすると出版料だけで400万や500万もかかってしまいます。その上で、研究者は論文を読むために同じ出版社から雑誌の講読料を取られます。場合によっては研究に使ったお金よりも、出版社に支払うお金のほうが高いことさえあるのです。
研究者自身が自分の研究の出版の是非をコントロールできず、著作権も持てず、にもかかわらず雑誌購読に高額の支払いを要求される。これは明らかにおかしいでしょう。大学も研究者コミュニティも、さすがに堪忍袋の緒が切れています。今回のF1000Researchとのオープンリサーチ出版ゲートウェイ開発は、この問題に対する筑波大学なりの問題提起です。
—アメリカやヨーロッパを中心に、海外の大学では学術出版社をボイコットする動きなどが広がっていますが、日本の大学がこの流れに具体的なアクションをとったケースは非常に少ないです。
日本の大学の人間も、個々には同じ問題意識を持っています。ならば欧米みたいにボイコットのような強いアクションを起こせばいいのにと思われるかもしれませんね。例えば、大学として特定の出版社の雑誌購読をボイコットするとか、ドイツのように「我が国の研究者はピアレビュープロセスに協力しません」と国として宣言するとか。でも本当にそれでいいんだろうか?「学問の主体を商業出版社から研究者に取り戻したい」と研究者の自主性を求めて声を上げているのにもかかわらず、政府や大学が研究者から文献を取り上げて、研究発展の基礎であるピアレビュープロセスに強制的に参加させないというのは、矛盾していておかしいと思いませんか?
さらに、日本特有の大学の事情があります。欧米のように私立大学が強い国と違って、日本の理系の研究は国立大学を中心に行われています。国立大学には日本の研究クオリティを守る責務があり、大学の方針を優先して教職員や学生たちのライフラインである研究情報にアクセス制限をかけるのが本当に正しいのかという問題がある。たとえ大手出版社に反旗を翻したいからといって、国立大学が本来持つ公共性の部分がそれを許さない文化があるのです。その行動が学者に学問を取り返すどころか学者の仕事の妨げになっては本末転倒ですから。
—今回F1000Researchと開発したゲートウェイは、世界で初めて日本語による出版を可能にしたことも大きなポイントです。
それがまさに現代の学術出版の第三の問題です。グローバル化の中で人文社会科学、人間科学研究が日本語で研究発表することの不利さはこれまで拭えないままきました。例えば英文学なら英語で論文を書くし、ドイツ語研究ならドイツ語で書き、日本語研究なら日本語で書く。それは当たり前のことで、何語で書かれていようが、少なくとも最低限の学術情報は国際ステージに上げて世界中の誰にでもアクセスできる状態にするべきだと思います。その情報に価値を見出す人は、原文が外国語だとしても問い合わせる手段があるからです。今はその論文の存在を伝えるプライマリーな情報すら国際的なデータベースに共有されていない。これは大問題です。
研究は今や国や専門分野を超え、国際的かつ学際的に動いていて、人文社会学も例外ではありません。新型コロナウイルスの研究を見ればわかるでしょう。我が国だけ、特定分野だけ、という限られたくくりで新しい研究をすることはもう難しい時代です。出版言語の垣根を超えた出版プラットフォームを作ることは、分野や地域の分断を超える手段の一つとして、大きな意味があると思います。筑波大学は総合大学として、人文社会学系の研究者の価値をより世界に知ってもらうために何かしら工夫していかなければならないと考えてきました。今回作ったゲートウェイでは日本語の論文の投稿も可能で、一定の条件を満たせば国際的な論文データベースに論文がインデックスされる仕組みです。もちろん、これは一つのきっかけに過ぎず、人文社会学分野の出版と研究評価の問題にはもっと多くの改革が必要なのは言うまでもありません。
—今回の筑波大学の試みは、大学が出版社に頼らない学術出版の方法を提案することで、間接的に現代の学術出版の課題に問いを投げかけた新しいやり方のように見えます。なぜ踏み切れたのでしょうか?
「なぜ筑波大学が?」という疑問ですよね。これは筑波大学の建学の理念が大きいのです。「システムの不断の改革」は我々の大学が建学以来守り続けているミッションです。日本の旧制大学が1947年に新制大学に変わって今の国立大学の歴史が始まったわけですが、筑波大学はそれから遅れること26年後、1973年にできた最も新しい国立大学です。旧体制を壊し、堅苦しいシステムを問い直して改善すること自体が我々の大学の存在理由の一つなのです。成功するか否かを問う前に、改革マインドを持たなければいけない、というのが大学のスタンスとして徹底している。それが筑波大学の役割ならば、すべての大学が共通の問題として抱えているこの学術出版の問題は放っておくわけにはいかない。リスクを負ってでもやるべきことはやらなければ、というのが本音の理由です。
そして筑波大学のいいところは、同じ教育研究理念を持った人たちが集まっていて小回りが効くことです。今回のゲートウェイの導入は僕らにとっては学内コンセンサスがとりやすいレベルの改革でした。大学全体で「筑波大学の研究者は今後一切ピアレビューに参加しません」と宣言するのは難しいし、他大学の経営者や研究者も巻き込んでしまいますが、「オープンリサーチ出版ゲートウェイで斜めから勝負を仕掛けてみようか」というのは大学単位でできる比較的ミニマムな決断だったと思います。
—オープンパブリケーションが進んだ場合、大学ランキングに代表されるような「英語で勝負できて、影響力が大きいジャーナルに多くの論文が載った大学が勝ち」という大学評価のあり方は変わる可能性があるのでしょうか?学長自身、大学ランキングをどう考えていますか?
オックスフォード大学の学長と大学ランキングについて話した時、彼の回答は明快でした。「大学ランキングってのは、しょうもないよね。でも1番になるのはうれしいんですよね」と。僕もまさにその通りなんだと思います。つまり、ほとんどの大学はランキングが大学内外に一定の影響力があることは認めているものの、それが大学の教育研究の仕組みを動かすほどのものだとは思っていないと思うんですね。ランキングを上げることに重きを置いてしまったら本当になんにもならない。でも「たかがランキング、されどランキング」、その「されど」がオックスフォードの言うやっぱり1番はうれしい、という部分なんです。人間って、洋の東西を問わずに、ランキングの上位に上がるのが大好きなんですよ。僕らも当然ながら、その嬉しさのせいでいつの間にかのせられてしまうわけです。
僕は現在の大学ランキングの存在意義はいずれ失われていくと考えています。ランキング会社が毎年データベースやメソドロジーを変えるたびにランキングが上がったり下がったりするのを大学は経験しているので限界も見えているし、結果への信憑性はすでに薄れてきているわけです。その代わりに、僕はAI技術などを使って、人々が気づいていない大学の個性や魅力を掘り起こして、学生のニーズとマッチングするようなアプリが今後生まれる可能性があると思います。現在のランキングは評判調査とかCitationとか、誰かが決めた偏った指標に基づいて決めているわけですが、AIの世界ではもっと全方位的に、見る人の興味にあわせてカスタマイズされた全く違う次元のランキングを作ることができるはずです。大学の情報がそのようにオープン化されれば、THEやQSなどが権威づけすることで成り立つ大学ランキングというビジネスは役割を終えると思います。各大学もまたそれぞれにIRを推進して、自分たちの強みと弱みを分析して世間に自ら開示していく方向に傾いていくと思います。
—現場の職員の方々は、今回のF1000Research導入の実現には、学長が「面白いじゃないか。失敗をおそれずとにかくやってみよう」と後押ししてくれたことが大きかったとおっしゃっていたのが印象的でした。ご自身の学長としての経営方針について教えてください。
僕は、「どこに出しても恥ずかしい学長」なんですよ(笑)つまり、旧体制に従わないタイプの人間です。ああしたい、こうしたい、変えなきゃいけない、とみんなが思っていてもやれないことってたくさんあります。大学を変えることは、僕にとっても難しいこと、できないことばかりなんです。でも誰かが凝り固まった社会の根幹を変えなければいけない。その僕自身の思いと、筑波大学の改革の理念がうまく一致していると思います。僕一人でやっても大学は変わりません。大学という組織全体が変わるためには、「変えたい」と思う人たちを応援してバックアップする体制がなければならない。たとえ教職員から100%の賛同を得られなくてもそれは当たり前なのです。何人かの賛同者が力を貸してくれて、組織を小回り良く着実に変えていける、筑波大学はそんな大学だと思います。
筑波大学学長 永田恭介教授 プロフィール
1953年生まれ。薬学博士。1981年に東京大学薬学研究科博士課程を修了。2001年より筑波大学基礎医学系教授。2009年に横浜市立大学との共同研究でRNAポリメラーゼの構造を解明した。2013年に筑波大学学長(第9代)に着任し現職。専門分野は、分子生物学、ウイルス学。
This post is also available in:
 EN (英語)
EN (英語)